生活保護を受ける条件とは?デメリットや受給金額はいくらなのか計算する方法を解説
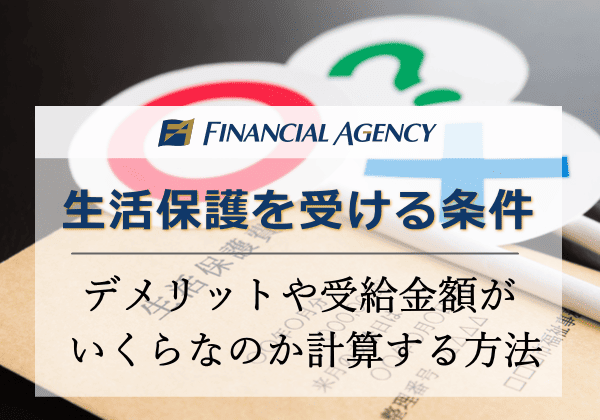
独立行政法人労働政策研究・研修機構の調べによると、生活保護を受けている人数は全国で2,010,289人(対前年同月0.6%減)、被保護世帯数は1,652,380世帯(同0.0%増)となっています。(令和6年8月現在)
生活保護を受けている人数は減少傾向にはあります。しかしながら、昨今の社会情勢の変化で個人を取り巻く経済環境は悪化しており、実際のところは生活保護を申請しないと生活していけない人も増えています。
一方で、ひとことで「生活保護」といっても制度の内容がわかりにくく「いったい、いくらもらえるのかわかりづらい」といった声も聞こえてくるのも現状です。
そこで本記事は、生活保護の基本的な仕組みや実際もらえる金額について、わかりやすく解説しています。
生活保護受給の5つの条件を詳しく説明

まず、生活保護を受給するための条件から解説します。
生活保護を受けるためには以下の5つの条件をクリアしている必要があります。
生活保護を受ける条件
1.世帯収入が最低生活費に満たないこと
2.病気などやむを得ない状況が原因で働けないこと
3.身内に経済的援助をしてくれる人がいないこと
4.生活保護以外の公的支援が受けられないこと
5.資産を持っていないこと
生活保護条件①世帯収入が地域の最低生活費に満たない
憲法第25条では、我々人間が健康かつ文化的な生活を送らなければならないと決められています。最低生活費とは、その生活を送るために必要な費用のことを指します。
下記に東京と北海道に住む場合を比較していますが、住む場所によっては物価や家賃も異なりますので、最低生活費も違ってきます。
【東京と北海道の最低生活費の差/ひとり暮らしの場合】
| 東京23区の場合 | 北海道函館市の場合 | |
|---|---|---|
| 生活扶助額 | 76,310円 | 71,460円 |
| 住宅扶助額 | 53,700円 | 30,000円 |
基本的には、上記の最低生活費の金額分が生活保護費として支給されます。(この金額以外にも、母子家庭に支給される金額など、いくつかの加算金額もあります)
一方、少しでも収入があると最低生活費の基準額から収入額を差引いた額が、生活保護費として支給されます。
例えば、最低生活費が13万円の場合、アルバイト収入が3万円あると、実際に支給されるのは13万円-3万円=10万円となります。
※収入には、アルバイト収入のほかにも年金や失業保険、退職金や仕送りなどが含まれます。
生活保護条件②やむを得ない事情で働けない
現時点で世帯収入が最低生活費未満だったとしても、家族のなかで働ける人がいる場合、原則生活保護が認められないことがあります。
生活保護を受給するためには、病気や障害が原因で「働きたくても働けない」ことが条件となります。
なお、単に「仕事が見つからないから働けない」「働きたくない」といった事情では、生活保護の申請は難しいでしょう。
病気などで働けない場合は、病院で診断書をもらう必要がありますし、障害を持っている場合は障がい者手帳を申請時に提出する必要もあります。
生活保護条件③身内に援助してくれる人がいない
例えば、生活保護を申請する人が高齢の親で、近隣に親を経済的に援助できる子どもや親族がいる場合は、生活保護の対象にはなりません。
生活保護では、公的支援を受ける前にまずは身内からの経済的な支援が優先されます。親族から支援してもらって安定した生活を送れる人は、受給の対処になりません。
ただ現実は近隣に身内がいても連絡がとれなかったり、十分な調査を行うのには限界があります。そのため、身内の支援能力を確認できないのが現状です。
この点については過去に参議院でも議論され、以下のとおり「身内がいるかどうかは別にして、申請世帯が経済的に困窮しているかどうかが優先される」とされています。
〈参議院公式サイト/厚生労働委員会調査室/生活保護の現状と課題より〉
生活保護の支給を受けるには、要保護者等が申請を行わなくてはならない(申請保護の原則)16。申請が行われると、要保護者について、保護の補足性の原理17に基づき様々な検討、調査が行われる。保護の補足性の原理とは、資産、能力等あらゆるものを活用することを保護の要件とする原則である。
活用すべきものの具体例としては、不動産、預貯金等の資産、稼働能力、年金や手当等の社会保障給付、扶養義務者からの扶養等が挙げられる。
〈扶養義務の徹底〉
特段の事情がない親子で、子が明らかに親を扶養可能であるにもかかわらず仕送りを拒否し、親が生活保護を受給している場合、個別の家族の事情を考慮しつつ、生活保護制度への信頼を損なわないようにすることが求められている。
旧法は保護の対象から扶養をなし得る扶養義務者を有し急迫した事情がない者を除外していたのに対し、現行法は、無差別平等の原則59により、専ら生活に困窮しているかどうかという経済状態だけに着目して保護を行うこととしている。
(引用元:生活保護の現状と課題「より公正、公平な生活保護制度の構築に向けて」厚生労働委員会調査室/内藤 俊介/立法と調査 2012.8月資料)
生活保護条件④生活保護以外の公的支援が受けられない
国の支援のなかには生活保護以外にも、さまざまな公的支援があります。
生活保護は、あくまでも最低限の生活を送るための最終手段とされていますので他の公的支援で生活が送れる場合は生活保護を申請しても原則認められません。
生活保護以外の公的支援としては、以下のようなものがあげられます。
〈厚生労働省公式サイト/生活保護制度より〉
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
(引用元:「生活保護制度」厚生労働省)
【生活保護以外の公的支援の例】
| 老齢年金 | 障碍者年金、遺族年金など65歳以上の人が受け取れる年金、障害や病気によって生活や仕事が困難になった人がもらえる年金、年金加入者が死亡した場合に家族が受給できる年金など |
| 失業保険や労災保険 | 失業者に支給される保険金、業務時間中や通勤の途中で事故にあった場合に支給される保険金など |
| 求職者支援資金融資 | 現在求職中の人が利用できる生活費補填のための支援制度 |
| 生活福祉資金貸付制度 | 生活再建の目途はあるものの、急な失職や災害などで働けなくなった人のための国の貸付制度 |
ちなみに、年金で支給される金額が最低生活費に満たない場合は、足らない金額分を生活保護費で受給することは可能です。
生活保護条件⑤土地、建物、車などの資産を持っていない
職を失って生活費に困っているものの「高級車に乗っている」「現預金や換金できる貴金属を持っている」といった場合、まずは生活保護を申請する前に資産を売却して現金化することが求められます。
資産のなかでも、最低限生活に必要な以下の資産については処分する必要はありません。
【処分しなくてもよい資産の例】
| 現金 | 10万円未満の少額現金 |
| 家電製品 | エアコンやストーブ、電子レンジや冷蔵庫など生活に必要な家電 |
| 家財道具 | スマートフォンやパソコン、自転車・食卓など |
| 介護用品 | 車いすなど |
また車やバイクなどは原則売却が求められますが、障がい者で車がないと生活ができなかったり、車でないと生活ができない過疎地などにおいては自動車の保有が認められることがあります。
住宅については生活保護費で各種ローンを返済することは認められていないため、ローン残高があると自宅の売却が求められます。
一方ローンの支払いを終えている場合、住んでいる家は最低限生活を営むうえで必要不可欠なものとみなされますので、生活保護受給のためにわざわざ売却しなくてもよいことになっています。
厚生労働省公式サイト/生活保護Q&A
【質問】ローン付住宅を保有している者から保護の申請があったが、どのように取り扱うべきか?
【回答】ローンにより取得した住宅で、ローン完済前のものを保有している者を保護した場合には、結果として生活に充てるべき保護費からローンの返済を行うこととなるので、原則として保護の適用は行うべきではない。
(引用元:厚生労働省)
生活保護の仕組みともらえるお金の種類を説明

以上が、生活保護受給のための基本的な条件です。
ここからは、生活保護の基本的な仕組みや加算されるさまざまなお金の種類について詳しく解説します。
上記で基本的な生活扶助額について触れましたが、実際には基本額に加えて教育費や医療費などが別途支給されます。
生活保護がもらえる仕組みや法律
生活保護は、さきほど触れたとおり憲法で「国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定されたことにより制定された「生活保護法」により運営されています。
生活保護法では、以下の基本的原則が定められています。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
(無差別平等)
第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
(最低生活)
第三条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
(引用元:法令検索e-GOV生活保護法)
生活保護費のなかにはたくさんの種類がある
ひとことで生活保護費といっても、冒頭で触れた生活扶助費(基本的な支給部分)のほか、教育費・医療費・介護費・住居費など、さまざまなお金が支給されます。
なかには、必要なものを現物で支給したり実費支給されるものもあります。
一見すると生活保護の基本額は少ないように見えますが、実際には生活するのに最低限必要な金額が支給されます。
基本的な生活を送るための生活扶助費用
「生活扶助費」とは食費や衣服を買うためなど、最低限日常生活で必要なお金のことを指します。
生活扶助費は生活保護の基本部分となり、地域によっては物価が異なり必要とする人数もバラバラなことから、住む場所と家族の人数により支給額は異なります。
たとえば東京と地方都市を比較した場合、家族の人数や年齢で以下のような差があります。
【生活扶助額の例】
| 東京都区部など | 地方群部など | |
|---|---|---|
| 3世帯 (33歳、29歳、4歳) | 164,860円 | 145,870円 |
| 高齢者単身世帯 (68歳) | 77,980円 | 68,450円 |
| 高齢者夫婦世帯 (68歳、65歳) | 122,460円 | 108,720円 |
| 母子家庭 (30歳、4歳、2歳) | 196,220円 | 174,800円 |
※児童養育加算、母子加算、冬季加算Ⅵ区の5/12を含む
※引用元:R5.5生活保護に関するQ&A
住む場所を確保するための住宅扶助

住宅扶助は賃貸マンションを借りたりするなど、住む場所を確保するために支給される保護費です。先程の生活扶助費とは別で支給されます。
具体的な支給費の中身としては以下の表を参考にしてください。住宅扶助費も住む地域により家賃などが変わるため、居住地により支給額が変わってきます。
| 支給内容 | 支給額 |
|---|---|
| 【家賃、間代等】 借家借間に居住する被保護者に対し、家賃等や転居時の敷金、 契約更新などを補填するものとして支給 | 実費(地域に応じて上限額を設定) 単身世帯:53,700円 2人世帯:64,000円 3~5人世帯:69,800円 ※東京23区の場合 |
| 【住宅維持費】 居住する家屋の補修や、畳、建具等の従属物の修理、 豪雪地帯においては雪囲い、雪下ろし等に必要な経費を 補填するものとして必要を要すると認定された場合のみ支給 (補修規模は、社会通念上最低限度の生活にふさわしい程度) | 年額122,000円 |
最低限義務教育を受けるための教育扶助
義務教育を受けている子どもがいる場合、給食費や教材を購入するためのお金も必要になります。生活保護を申請すると、該当する世帯には生活扶助費とは別で教育扶助費も支給されます。
具体的な費用の中身は以下の通りで、交通費や学校で必要となる物品代など多岐にわたります。
【支給内容】
小学生、中学生に対し、義務教育にかかる必要な学用品費や教材代、給食費等を補填するものとして支給
(※ 修学旅行代は文部科学省の就学援助制度から支給)
【支給額】
基準額(月額):小学校等2,600円、中学校等5,100円
■教材代/学校給食費/交通費…実費
■学習支援費(クラブ活動費/年額)…実費(小学校等上限額 1万6,000円以内、中学校等上限額 5万9,800円以内)
(引用元:生活保護制度の概要等について)
医療費が支給される医療扶助
医療扶助は、病気などで診察や治療が必要になった時に支給される保護費です。実際にはお金が支給されるわけではなく、医療券をもらうことで医療サービスが受けられる仕組みになっています。
生活保護を受けている人が病院などで治療を受ける場合の流れを以下にまとめていますので参考にしてください。
生活保護受給者が病院にかかる時の流れ
STEP❶ 日程調整:医療機関と受診日を決める
STEP❷ 連絡:地域の福祉事務所へ連絡する
STEP❸ 医療券:福祉事務所で医療券を受け取る
STEP❹ 受診:医療機関で受診する
介護が必要になったときにもらえる介護扶助
介護扶助は、生活保護費の受給者が介護サービスを受ける際に利用できる生活保護費の一種です。
具体的には、介護サービスの利用料や病院の治療費などが発生する場合に補助が受けられます。
ただ、実際に支給されるのはお金ではなく現物支給にて補填が行われます。
出産費用がもらえる出産扶助
出産する時には自宅分娩や病院での分娩に関わらず、かなりの出費が伴います。生活保護を受けている人が出産する時は、出産扶助費が受け取れます。
以下の通り支給額は実費で上限額も決められていますが、生活扶助費とは別に支給されますので安心して出産に臨めるでしょう。
| 施設分娩の場合 | 実費(上限額30万6,000円以内) |
| 居宅分娩の場合 | 実費(上限額25万9,000円以内) |
自立するために仕事スキル習得に使える生業扶助費
生活保護を受けていても、基本的には働ける状態なら仕事を見つけて給料を得る努力をしなければいけません。
生業扶助費では新しい仕事にチャレンジするための技能取得費用や、高校に通う為の費用を援助してもらえます。
具体的なもらえるお金については以下の表にまとめています。仕事に必要な運転免許を取得するための費用も上限38万円までで支給されますので、かなり手厚い制度と言えます。
【技能修得費】
生計の維持に役立つ生業につくために必要な技能
【支給額】
実費(上限額8万3,000円以内)
※以下の場合は38万円以内で実費
・生計維持に役立つ生業に付くため専修学校等で技能を修得し、自立助長に資することが確実に見込まれる場合
・免許取得が雇用条件である等確実に就労に必要な場合に限って、自動車運転免許を修得する場合
・雇用保険の教育訓練給付金の対象となる厚労大臣が指定する講座を受講し、自立助長に効果的と認められる場合
(原則講座修了によって自立助長に効果的な公的資格が得られるものに限る)
【高等学校等就学日】
高校生に対し、高等学校教育にかかる必要な学用品費や教材代、交通費等を補填するものとして支給
(※修学旅行代は文部科学省の高校生等奨学給付金の活用やアルバイトなどにより負担)
就職支援費:就職が確定した者に対し、就職のために直接必要となる洋服代、履物等の購入経費、就職の確定した者が初任給が支給されるまでの通勤費を補填するものとして、必要な場合に支給
【支給額】
■基本額(月額)…5,200円
■教材代/交通費…実費
■学習支援費(クラブ活動費/年額)…実費(上限額8万3,000円以内) など
(引用元:生活保護制度の概要等について)
【就職支度費】
就職が確定した者に対し、就職のために直接必要となる洋服代、履物等の購入経費、就職の確定した者が初任給が支給されるまでの通勤費を補填するものとして、必要な場合に支給
【支給額】
32,000円以内
(引用元:生活保護制度の概要等について)
身内の葬儀費用に使える葬祭扶助費
葬祭扶助は、その名の通り身内に不幸があった際に支給される生活保護費です。上限は以下の通りで実費が支給されます。
| 大人 | 実費 (上限額21万2,000円以内) |
| 小人 | 小人 実費 (上限額16万9,600円以内) |
生活保護の申請から支給までの流れを説明

生活保護の仕組みや、もらえるお金については上記の通りです。
ここからは、具体的な申請手続きの方法について解説していきます。
STEP1.福祉事務所に相談する
生活保護を申請するときは、最初に地域の福祉事務所に相談が必要となります。
住んでいる地域のどこに福祉事務所があるのかについては、以下のリンクを参考にしてください。
申請すると窓口の担当者から就労に関することや、身内の援助など支給に必要な内容を聞かれます。
その結果、生活保護の申請対象と認められた場合は書類がもらえますので、必要事項を記入して窓口へ提出しましょう。
書類については、インターネットからでもダウンロードできます。
※参考:厚生労働省公式サイト/福祉事務所
STEP2.生活保護を申請し調査を受ける
申請が済むとケースワーカーによる調査が行われます。冒頭で触れた通り、生活保護を受給するためには資産を持っていないことが条件となります。
そのため、「申請者の申告通り本当に収入がなく資産もないのか?」といった事が訪問により確認されるのです。
具体的には預貯金や不動産の確認や、本当に働く事ができないのかなど生活の実態が調査されます。
また調査時には金融機関への確認も同時に実施され、預貯金の額も調査員に知られてしまいますので、決して虚偽の申告はしないよう注意しましょう。
嘘の申告で生活保護を受給すると、法に触れることになるからです。
STEP3.生活保護費の支給を受ける
ケースワーカーの調査で問題がなければ、最短で申請から14日後には生活保護費が支給されます。
ほとんどの自治体では月初が支給日です。ただし、調査で疑義が発生すると申請から1ヶ月程度かかる場合もありますので、その点は覚悟しておきましょう。(申請途中にお金が尽きた時に利用できる支援制度もあります。このあと触れます)
生活保護を受給していても働ける状態の人は、基本的に仕事をして収入を得ることが求められます。
ケースワーカーからも仕事をするように指導を受けますので、継続してハローワークなどで仕事を見つける努力は怠らないことが大切です。
生活保護費が待てない場合に利用できる臨時特例つなぎ資金貸付制度
上記の通り、生活保護を申請しても即日支給されるわけではなく申請から支給までには14日~30日程度かかります。
そのため、申請した人のなかには「お金がないから申請したのに支給が遅れると食べ物も買えない」といった人もいるかもしれません。
生活保護の支給までに時間を要し、たちまち生活が立ち行かなる場合は「臨時特例つなぎ資金貸付制度」の利用を検討してみましょう。
「臨時特例つなぎ資金貸付制度」の利用条件や概要は以下の通りです。
| 貸付対象 | 住居のない離職者であって、次のいずれの条件にも該当する方 (1)離職者を支援する公的給付制度(失業等給付、住宅手当等)又は公的貸付制度(就職安定資金融資等)の申請を受理されており、かつ当該給付等の開始までの生活に困窮していること (2)貸付けを受けようとする方の名義の金融機関の口座を有していること |
| 貸付上限額 | 10万円以内 |
| 連帯保証人 | 不応 |
| 貸付金利子 | 無利子 |
生活保護費の計算方法と実際の支給額を説明
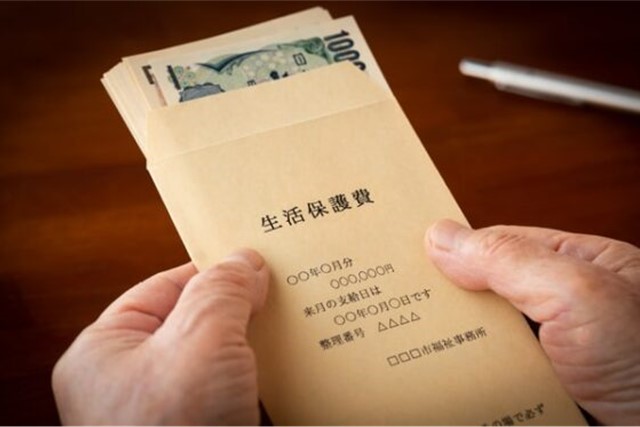
ここまでご説明した、基本的な生活扶助費の金額や、住宅確保のために支給される生活保護費をすべて計算するとどれくらいの金額になるのか、具体的に見ていきましょう。
世帯/地域別の生活保護費計算方法
生活保護費は「最低生活費ー収入」の差額が計算されて支給されます。そのため、仮に収入が0円だと最低生活費=生活保護費となります。
生活保護費の計算方法は、一見難しいように思いますが、以下の計算式で求められます。
生活扶助第1類+生活扶助第2類+その他の扶助=最低生活費
| 生活補助/第一類費 | 基本的な日常生活費のうち、食費や被服費など個人単位でかかる経費を補填するものとして支給 |
| 生活扶助/第二類費 | 第二類費 基本的な日常生活費のうち、水道光熱費や家具什器費など |
※参考:生活保護制度の概要等について
ただ、厚生労働省公式サイトでも少々わかりづらいと思いますので、参考までに東京都でひとり暮らしをしている50歳の人の例を表にしていますので、こちらも参考にしてください。
【東京都23区でひとり暮らしをしている50代の受給額】
| 生活扶助第1類 | 39,360円 |
| 生活扶助第2類 | 40,800円 |
| 生活扶助 | 53,700円 |
| 合計 | 133,860円 |
この計算でいくと、東京23区でひとり暮らしをしている50代の場合は、合計13万3,860円が支給されることがわかります。
加算してもらえるお金
生活保護費には、生活扶助や住宅扶助に加えて「加算額」も設定されています。
たとえば母子家庭だけに支給される「母子加算」や、障がい者に支給される「障がい者加算」などは代表的な例です。
以下に加算される費用項目と内容を表にしていますので、こちらも参考にしてください。
【生活保護費の加算額】
| 妊産婦加算 | 妊産婦(妊娠中及び産後6ヶ月以内)である被保護者に対し追加的に必要となる栄養補給などの経費を補填するものとして支給 |
| 母子加算 | ひとり親世帯のかかりまし経費(ひとり親世帯がふたり親世帯と同等の生活水準を保ために必要となる費用)を補填するものとして、ひとり親(母子世帯・父子世帯など)に対し支給 |
| 障がい者加算 | 障がい者である被保護者に対し、追加的に必要となる居住環境の改善のための費用や点字新聞などの雑費などの経費を補填するものとして支給 |
| 介護施設入所者加算 | 介護施設に入所している被保護者に対し、理美容品などの裁量的経費を補填するものとして支給 (例:嗜好品、教養娯楽費など) |
| 在宅患者加算 | 在宅で療養に専念している患者(結核または3ヶ月以上の治療を要するもの)である被保護者に対し、追加的に必要となる栄養補給のための経費を補填するものとして支給、 |
| 放射線障がい者加算 | 放射能による負債、疾病の患者である被保護者に対し、追加的に必要となる栄養補給等のための経費を補填するものとして支給 |
| 児童養育加算 | 児童の養育者である被保護者に対し、子どもの健全育成費用(学校外活動費用)を補填するものとして支給 |
| 介護保険料加算 | 介護保険の第1号被保険者である被保護者に対し、納付すべき介護保険料に相当する経費を補填するものとして支給 |
※引用元:厚生労働省公式サイト/生活保護制度の概要等について
生活保護の支給日について説明
生活保護の支給日についても、詳しい情報をお伝えしておきます。下記に江戸川区の例をご紹介しています。
このなかにもあるとおり、原則生活保護は毎月3日に支給され3日が日祝日の場合は前日が支給日となります。
【生活保護費の支給日について】
| 支給方法 | 世帯の状況によって判断し、以下の方法で支給 1.金融機関の口座への入金 2.福祉事務所の窓口での支払 3.入院入所している施設への送金 |
| 支給日 | 原則として毎月3日 (3日が土・日曜日または祝日の場合は直前の平日) ※異なる月もある |
| 賃貸住宅の家賃や共益費 | 不動産管理者に、福祉事務所から直接納める代理納付が可能な場合もある |
また、生活保護を受けている場合は、以下の出費についても免除が受けられます。詳しくはケースワーカーなどに相談してから手続きが必要です。
〈生活保護受給者が免除される費用の例/江戸川区の場合〉
・水道料金・下水道料金の一部(基本料金と一定の使用量。申請が必要)
・NHK放送受信料(免除/申請が必要)
・国民年金保険料(免除)
・住民税、固定資産税(減税)
・都営交通無料乗車券(記名式で世帯に1枚。申請が必要)
・東京都シルバーパスの使用(70 歳以上。本人負担 1,000 円。保護受給証明書が必要)
・粗大ごみ処理手数料(免除/保護受給証明書が必要)
・住民票、課税証明書、印鑑登録証明書の取得にかかる手数料(減免/保護受給証明書が必要)
・インフルエンザワクチン接種にかかる費用(免除/対象者に限る)
(引用元:江戸川区生活保護のしおり)
生活保護のデメリットについて解説

生活保護は、制限なしに誰もが気軽に受給できる制度ではありません。以下に生活保護を受けるときの「守るべきルール」を表にしています。
この表を見てもわかるとおり、節約をしたり仕事を見つける努力をしたり、さらにはケースワーカーの指導や調査に協力することが求められます。
厳しい言い方をすれば、援助してもらうかわりに「監視されることを覚悟しなければいけない」ことになります。
厚生労働省公式サイト/生活保護Q&A
【質問】生活保護の受給中、守らなければならないことはありますか?
【回答】生活保護を受給する方は、以下のような義務と権利があります。
<義務>
・利用しうる資産、能力その他あらゆるものを生活のために活用しなければなりません。
・能力に応じて就労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持向上に努めなければなりません。
・福祉事務所から、生活の維持向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示を受けたときは、これに従わなければなりません。
(引用元:厚生労働省公式サイト/生活保護制度に関するQ&A)
ケースワーカーの指導を受ける必要がある
生活保護受給中はケースワーカーが自宅に訪問し、さまざまな調査を実施します。
調査の目的は申請者の生活環境を確認したり、現金化できる資産がないかどうかをチェックするためです。
調査の結果、たとえば不動産や貴金属を持っている場合は売却するように指導される場合もあります。
なかにはケースワーカーに無理難題を押し付けて過剰なサービスを強要する事例も報告されていますが、スムーズに生活保護を受給し続けるためにはケースワーカーの調査には快く応じることが大切になってきます。
生活保護受給中の贅沢はできない
前述のとおり、生活保護は最低限の生活が送れない時に生活費を補填する目的で支給されます。
そのため生活保護を受給している間は、高価な車を購入したり貴金属を買ったりすることは原則認められません。
生活保護費で借金返済は許される?
受給した生活保護費を使って、借金返済をすることも認められていません。
そのため生活保護費を「安定収入」としてカードローンに申し込んだりもできませんので、つつましやかな生活を続けることが求められます。
住宅ローンを抱えたままで生活保護が受給できないのは、そのためです。
生活保護を受ける条件まとめ
生活保護の仕組みは一見するとわかりづらいかもしれません。
しかし、今回の記事でご紹介したとおり基本的な内容を理解すればそれほど難しくありませんし、わからない事は福祉事務所でもサポートしてもらえます。
昨今の社会情勢の変化で、基本的な生活を送ることが厳しい人も増えています。
生活困窮に陥った場合、生活保護を一時的に利用することも可能です。
どうしても生活が苦しいなら、働けるようになるまでの支援として、一度福祉事務所などに相談してみることをおすすめします。